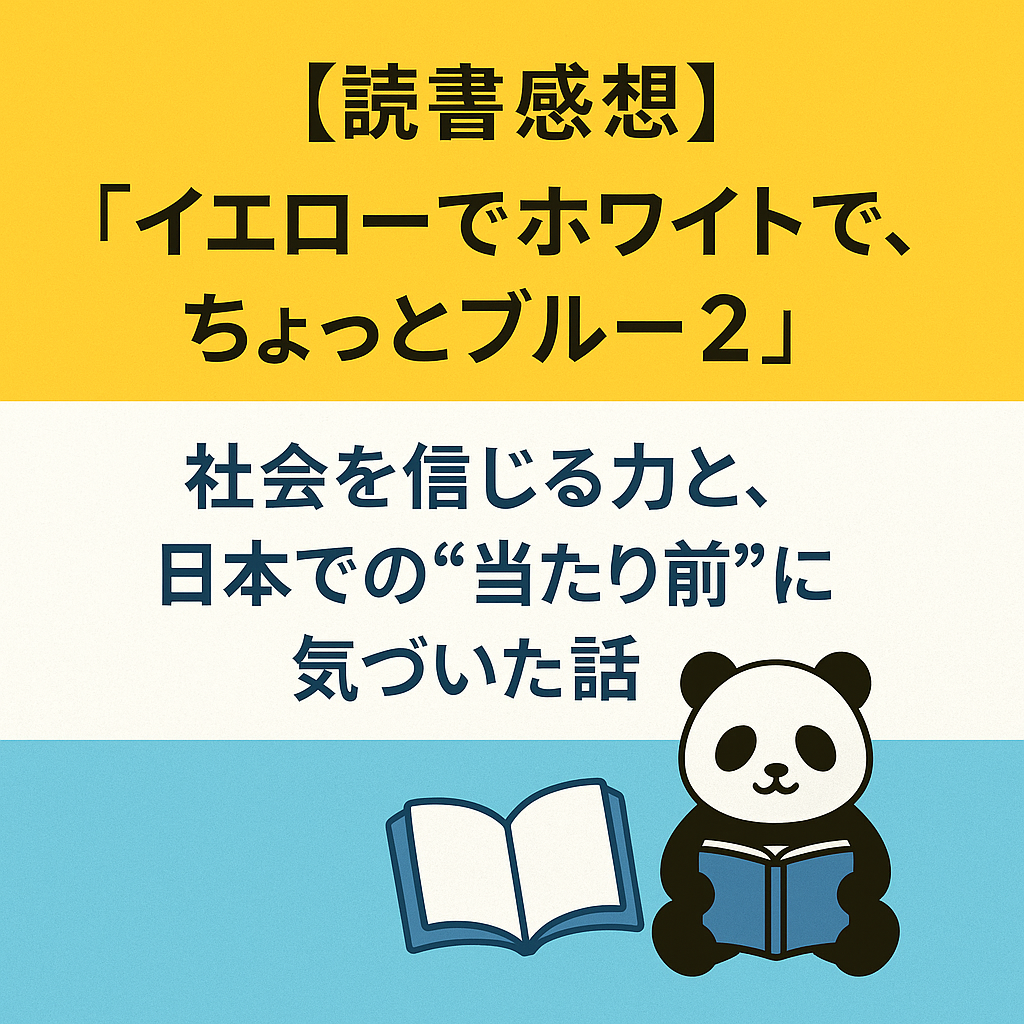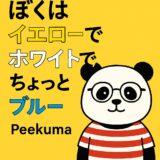社会を信じる力と、日本での“当たり前”に気づいた話
1. はじめに
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の続編を読みました。
前作では、「アイデンティティ」、「多様性」や「共感」などをテーマに、息子さんの中学校での出来事を通じて社会を見つめ直す視点が描かれていました。今回はその第2巻ということで期待しながら本を読み進めました。今回、「自分の意見を持つこと」「言葉で伝えること」そして「社会を信じること」が大きなテーマなのかなと私は感じました。
今回の感想では、特に印象に残った2つのエピソードをもとに、考えたことを綴ってみます。
2. 「女性とお年寄りばかりが車を運転している?」
イギリスから見えた日本のジェンダー観
母親の母国である日本に帰省した息子さんが、こんなことを言います。
「日本では、車を運転しているのが女性とお年寄りばかり。男の人はどこにいるの?」
この一言に、私はドキッとしました。
確かに、日中のスーパーの駐車場や道路を見ても、買い物や送り迎え、病院への通院などで車を使っているのは、女性や高齢者が多い気がします。
イギリスだって、もちろん男性も働いています。けれど、ケアや家庭内の役割が“女性だけのもの”になっていないという点では、日本とはバランスが違うのかもしれません。
「女性が支えるのが当たり前」とされている日本の空気。少しずつ世の中は変わっていこうとしていますが世界的な視点で見るとまだまだなのだと感じました。
そこには、ジェンダー観の偏りや、まだ変わりきれていない社会構造があると改めて気づかされました。
3. イギリスのスピーチ教育と「伝える力」
もうひとつ、印象的だったのが、息子さんの学校でのスピーチ課題の話です。
イギリスのGCSE(イギリスの義務教育修了試験)では、スピーチも国語の評価項目に入っているそうです。
生徒は、自分でテーマを決めてスピーチを書き、実際に話す様子を録画し、試験官に提出するのだとか。
その訓練として、授業では「5Sメソッド」という構成法が教えられています。
5Sメソッド
- Situation(現状)
- Strongest point(もっとも言いたいこと)
- Story(エピソード)
- Shut down(反論を予測し、封じる)
- Solution(提案や結論)
この構成、正直、日本の国語教育でも取り入れてほしいと思ってしまいました。
自分の意見を組み立て、声に出して伝える。
それは、ただ“作文を書く”以上に、社会の一員としての視点や責任感を育てる力なのかもしれません。
4. 息子が伝えたかったのは「ホームレス問題」ではなく「社会を信じること」
息子さんが選んだスピーチのテーマは「ホームレス問題」でした。
きっかけは、日本の避難所でホームレスの人が受け入れを拒否された、というニュース。
また、普段から図書館の建物にホームレスが入れないことに疑問を感じていたそうです。
最初は身近な問題であるこちらをテーマに考えたようですが彼は、そのテーマに反感を持たれるかもしれないと考え、より“遠い国の問題”として日本の避難所でのニュースをテーマに取り上げたそうです。
それでも、彼が本当に伝えたかったのは「ホームレス問題」そのものではなく、
「社会を信じる」
という問いだったのです。
自分の言葉で、社会と向き合おうとする姿に、私は胸が熱くなりました。
5. おわりに|ぴーくまとして感じたこと
『イエローでホワイトで、ちょっとブルー2』を読み終えて感じたのは、「違和感に気づくことは、やさしさの始まり」だということ。
息子さんの視点は、私たち日本で暮らす人にとって「当たり前」になっている風景を、そっと揺さぶってくれます。
その揺さぶりはときに痛みを伴うけれど、それを受け止めて考えることが、きっと社会を変える一歩になるのだと思いました。
私も、ぴーくまブログを通して、「気づく」「考える」「伝える」ことを続けていきたい。
そんな気持ちになれる一冊でした。
📘ぴーくまの本棚シリーズはこちら
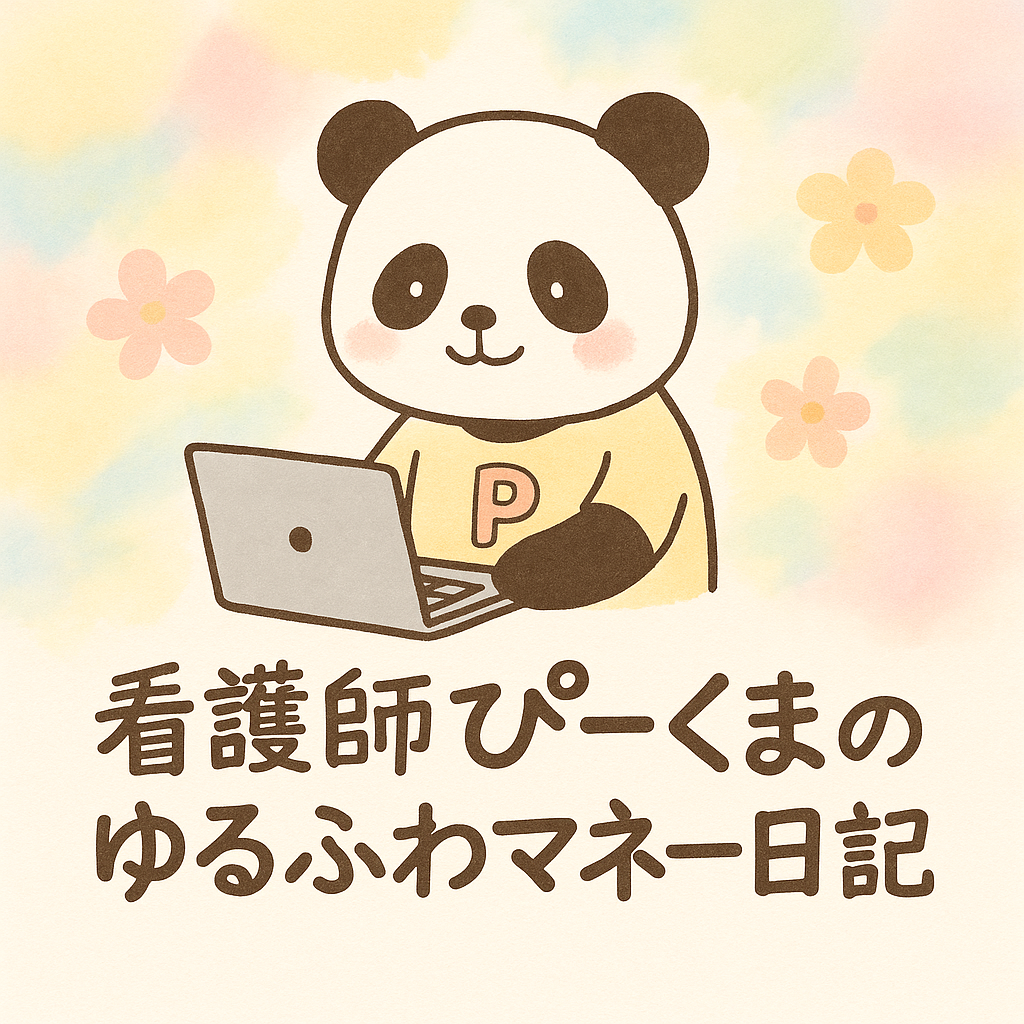 看護師ぴーくまのゆるふわマネー日記
看護師ぴーくまのゆるふわマネー日記