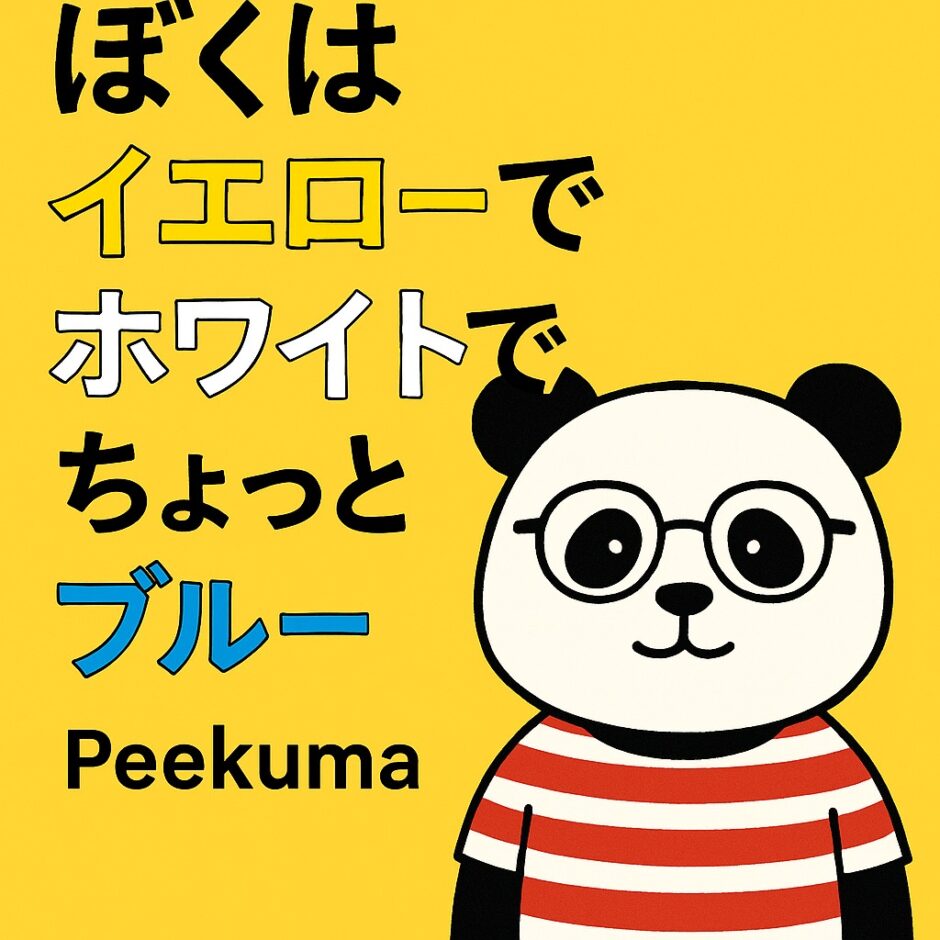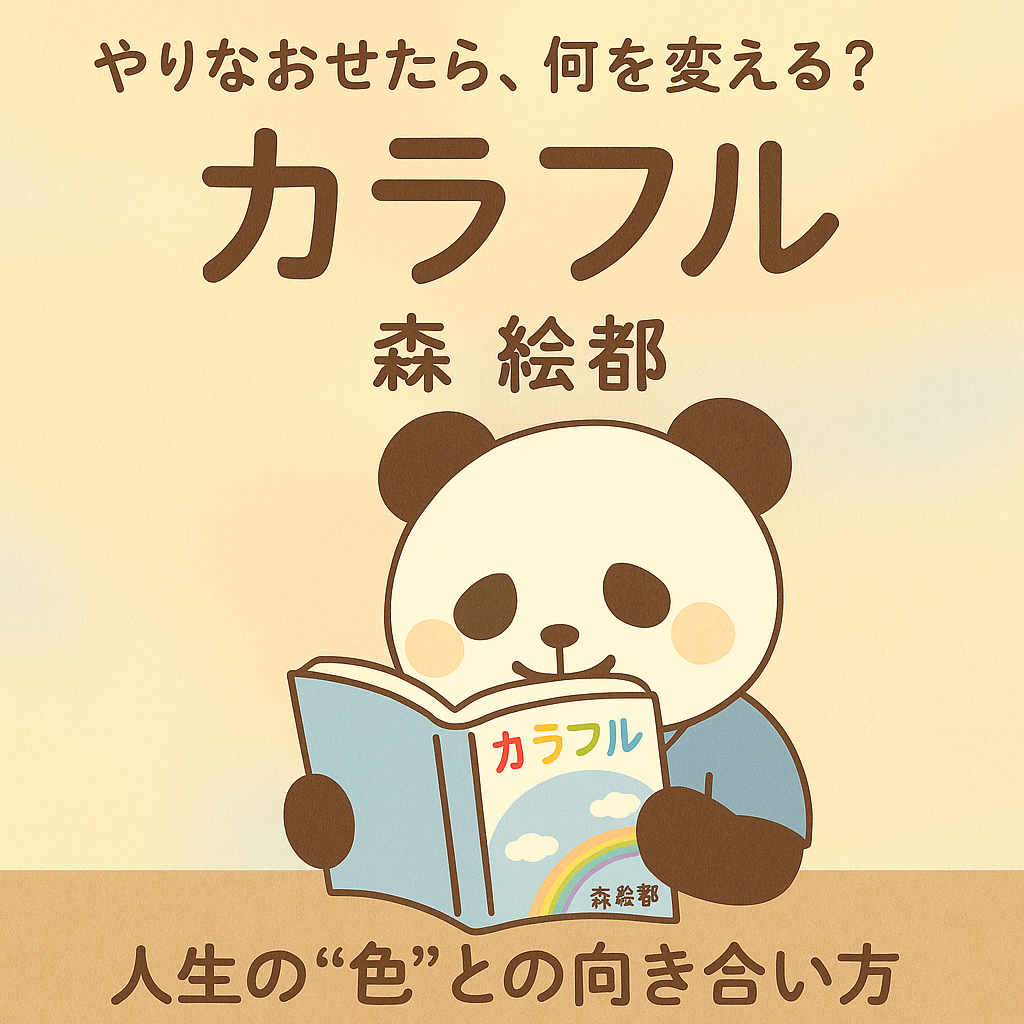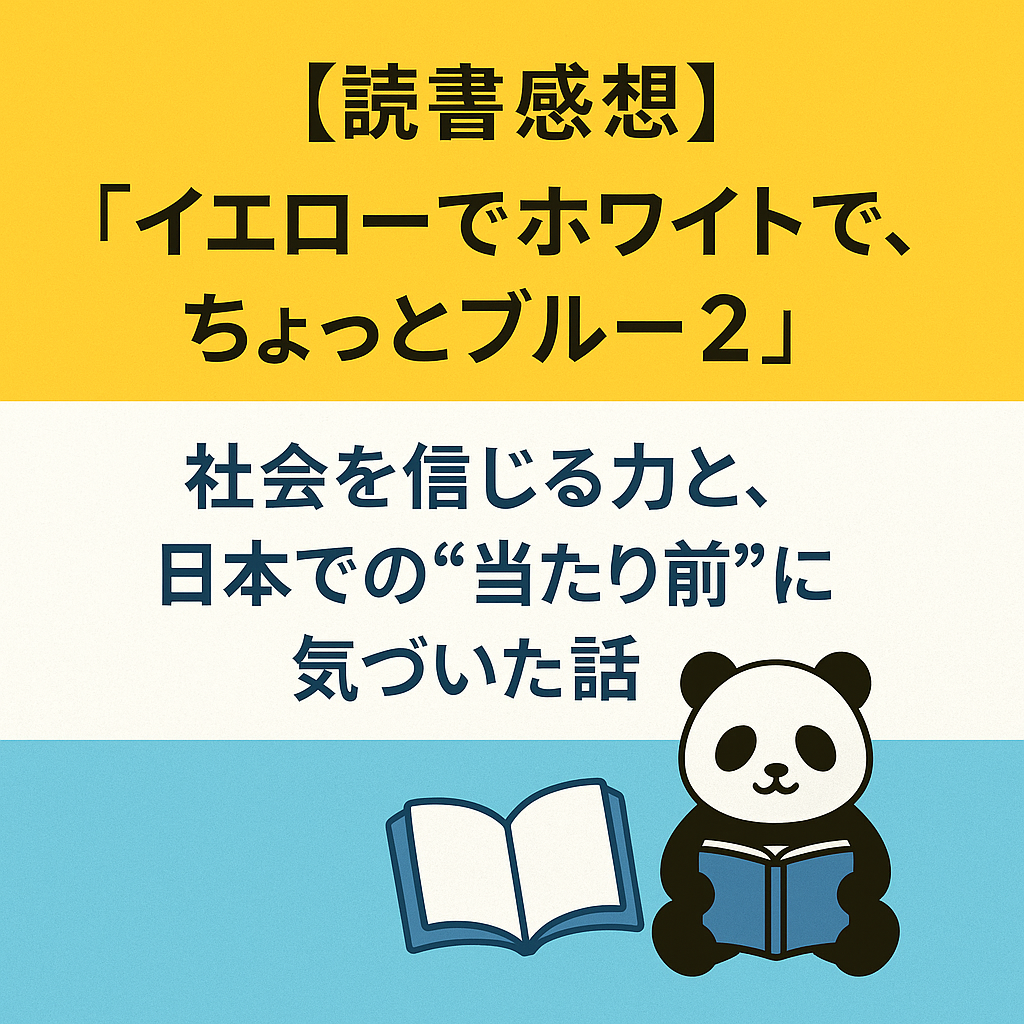目次
アイデンティティ、多様性、そして共感を考えるきっかけに。
1. はじめに
ちょっと前に話題になっていた本。
タイトルってどういう意味?と気になっており、なかなか手を出さなかったのですが、今回やっと読んでみました。
読んでみると、思っていた以上に深いテーマが詰まっていました。
これは、イギリス在住の著者とその息子の「リアルな日常」を描いたエッセイ。
でも、ただの親子日記じゃありません。
「違い」とどう向き合い、どう生きるか?
そんな問いかけが、ユーモアとあたたかさのなかに、何度も浮かび上がってきます。
私も、「自分ってなんだろう?」「人との距離感ってどうすればいいんだろう?」と感じるのが多くなっていたので、この本を読み、いくつものヒントをもらいました。
2. 著者紹介
ブレイディみかこさん
保育士でありライター。
福岡県出身の日本人で、現在はイギリス・ブライトン在住です。アイルランド人の夫、そして息子との家族3人暮らし。
イギリスの保育現場や社会問題を長年見つめてきた視点と、
母としてのあたたかなまなざしが、この本にもあふれています。
本作では、息子の通う元“底辺中学校”でのエピソードを通じて、イギリス社会の抱える問題や教育の取り組みが描かれます。
3. この本の背景
舞台は、イギリス・ブライトン郊外。
息子は、カトリックの小学校に通っていましたが、中学から元“底辺中学校”に入学します。
人種の多様性があるのは“お金持ちで優秀な学校”だけ。カトリックの小学校は人種の多様性がありました。息子が通う元底辺中学校は、ほとんどが白人の子どもたち。そんな中、東洋人の母・アイルランド系の父をもつ息子は、自らをこんなふうに表現します:
「ぼくはイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー。」
それは、英語の授業のノートに書かれた、自分のアイデンティティについてのひとこと。
「イエロー=東洋人」「ホワイト=白人」「ブルー=悲しみまたは気持ちが塞ぎ込んでいるような状態」。
息子は、“自分”のアイデンティティに対して何かしら悩み、考えていることがわかります。
4. 印象的なエピソード
●「人間は罰したい生き物」なのか?
息子の友人ティム(貧困家庭出身)と、ダニエル(ハンガリー移民出身)が喧嘩したときの話。
「貧乏人」「ハンキー(差別用語)」という言葉が飛び交い、学校側は差別用語を使ったティムをより厳しく処分しました。それがきっかけとなり、いじめがおきました。
息子がぽつりと漏らしたひと言が印象的です。
「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。・・・・・・・罰するのが好きなんだ。」
正義の名のもとに罰することで、自分の優位性を保とうとする構造。
そこには、子どもの世界に限らず、社会全体に潜む感情のメカニズムがあるのかもしれません。
5. 心に残った言葉や視点
●「共感=同意」じゃない
本の中で紹介される“シティズンシップ・エデュケーション”(日本だと公民や市民教育のこと)というイギリスの授業では、「エンパシー」と「シンパシー」の違いを学んだことを紹介されていました。
- エンパシー(Empathy):自分とは異なる立場の人の気持ちを想像する力
- シンパシー(Sympathy):同じ気持ちに共鳴すること
共感とは「わかるよ」と寄り添うだけじゃない。他者の立場を想像することも、大切な力なんですね。
それから、イギリスでは「演技」の授業があることも驚きました。
●ジェンダーの多様性を当たり前に
「タンタンタンゴはパパふたり」という絵本では、2羽のオスのペンギンが、拾ってきた石を卵のように温め、赤ちゃんを育てるストーリーが紹介されます。
子どもたちは誰も違和感を持ちません。
「この形が普通」「これが正しい」という“固定観念”が、大人よりもずっと少ないのかもしれません。
6. まとめ|ぴーくまのひとこと
この本は、”優しさ”や”正しさ”が簡単に決めつけられない世の中で、どう生きていくかを考えるきっかけをくれました。
看護師という仕事柄、人の違いに触れることが多い私にとって、「エンパシー」の力をもっと育てたいと感じました。
そして、息子さんのひと言がずっと残っています。
「ぼくはイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー。」
どこか不完全で、でもとてもリアルな「自分らしさ」。
誰かにラベルを貼られる前に、自分のことを言葉にできるって、なんて素敵なんだろう。
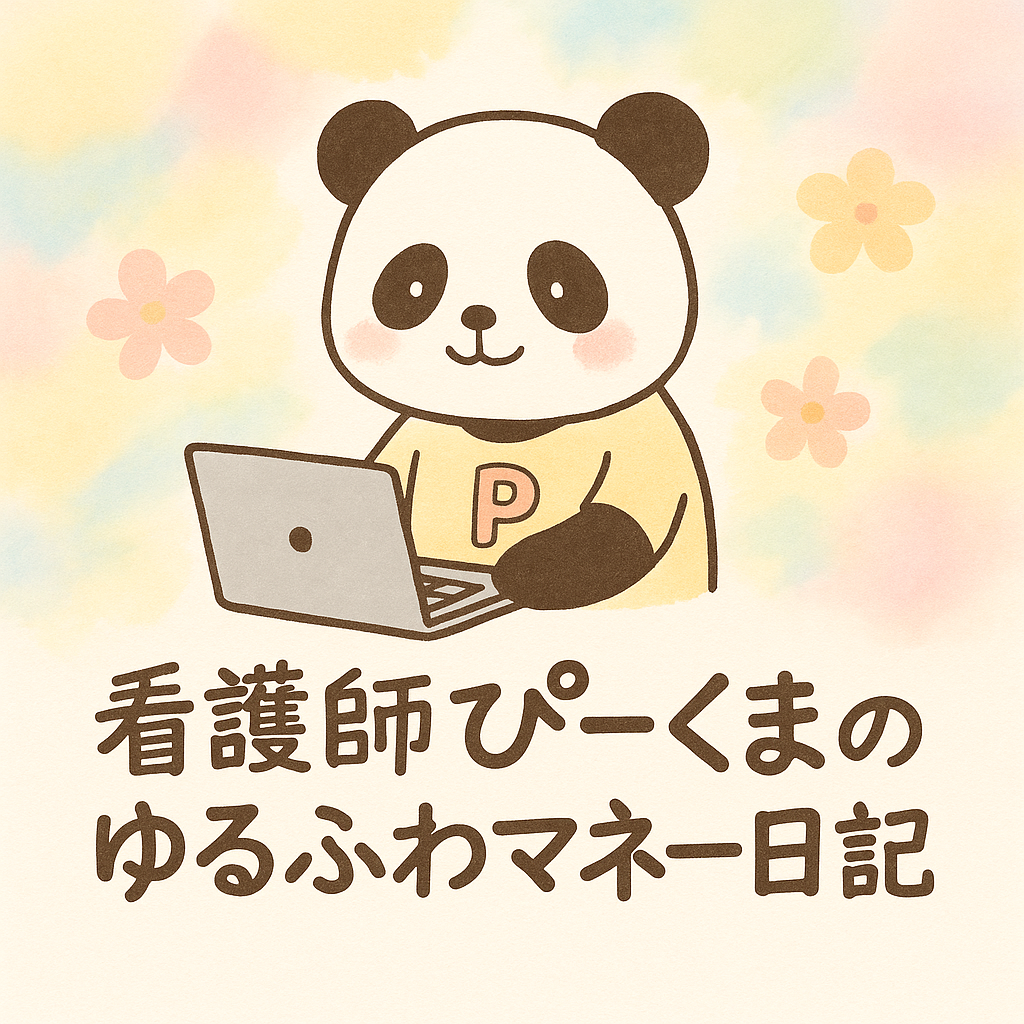 看護師ぴーくまのゆるふわマネー日記
看護師ぴーくまのゆるふわマネー日記